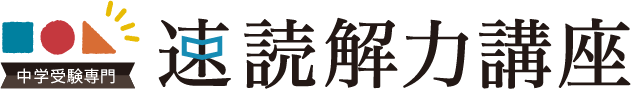「全国統一小学生テスト」がスタートして19年目を迎え、のべ400万人以上の小学生が受験している(四谷大塚発表)とのことです。
これまでに全国統一小学生テストを受験させたことのある保護者の方も多いのではないでしょうか。
一方で「全国統一小学生テストを受けてみたけど、時間が足りなくて思うように解けなかった!」「あっという間に試験時間が終わってしまった」という声も毎回のように届きます。
全国統一小学生テストの制限時間と文字数、問題の特徴などについて簡単にまとめました。
試験で時間が足りないということがないようにするための対策についても解説していきます。
【関連記事】 全国統一小学生テストの結果が出たら!国語の成績を上げる「正しい見直し・解き直し」を読解力のプロが解説
全国統一小学生テストとは
全国統一小学生テストは、四谷大塚が主催する学力テストで、年に2回、無料で実施され、小学生であれば誰でも受けることができます。
2007年度に開始され、のべ400万人以上が受験している日本最大規模のテストです。
テストの内容は小学校の各学年の範囲内から出題されますが、難易度は比較的高く、また文章量や問題量が多いため、かなりテンポよく解き進めなければ、試験時間で最後まで解き切ることはなかなか難しくなっています。
全国統一小学生テストの実施教科・配点・試験時間
各学年の実施教科、配点、試験時間は以下の通りです。
年長生も受験できますが、ここでは割愛いたします。
| 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生 | 30分・150点 | 30分・150点 | – | – |
| 小学2年生 | 30分・150点 | 30分・150点 | – | – |
| 小学3年生 | 35分・150点 | 35分・150点 | – | – |
| 小学4年生 | 40分・150点 | 40分・150点 | 20分・100点 | 20分・100点 |
| 小学5年生 | 50分・150点 | 40分・150点 | 25分・100点 | 25分・100点 |
| 小学6年生 | 50分・150点 | 40分・150点 | 25分・100点 | 25分・100点 |
小学3年生までは国語と算数のみ、小学4年生以降は理科と社会も実施します。
1年生は配点の70%、2・3年生は60%、4・5・6年生は55%が平均点となるように、試験問題が作成されています。
なお、1・2年生は記述式で、3~6年生はマークシート形式で解答します。
全国統一小学生テストの各教科の文字数
ここでは、2024年6月に実施されたテストの各教科の文字数を数えてみました。
以下のような結果となりました。
問題文だけでなく、選択肢なども含めた文字数で、テストを解くうえで読む必要のある文字数です。
| 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生 | 約2,000文字/30分 | 約1,600文字/30分 | – | – |
| 小学2年生 | 約3,000文字/30分 | 約4,000文字/30分 | – | – |
| 小学3年生 | 約4,000文字/35分 | 約6,800文字/35分 | – | – |
| 小学4年生 | 約4,500文字/40分 | 約8,000文字/40分 | 約4,700文字/20分 | 約5,400文字/20分 |
| 小学5年生 | 約5,500文字/50分 | 約9,200文字/40分 | 約6,100文字/25分 | 約5,300文字/25分 |
| 小学6年生 | 約4,800文字/50分 | 約10,600文字/40分 | 約8,300文字/25分 | 約7,600文字/25分 |
2025年度の御三家中学の入試問題で一番文字数の多かった桜蔭中学の国語が約11,200文字(50分)、その次に多かったのが麻布中の国語で約11,000文字(60分)でした。
小6の全国統一小学生テストの国語ではそれに匹敵する文章量が出題されているという結果です。
もちろん、全国統一小学生テストがマークシートであるのに対し、御三家中の国語は記述問題を書かなければいけないので、単純比較はできませんが、出題されている分量だけに注目すれば、全国統一小学生テストを受験している多くの小学生が「時間が足りない!」と感じてしまうのは無理もない数字と言えるでしょう。
全国統一小学生テストで求められる読書速度は?
この数字をもとにして、問題を最後まで解き切るために必要な読書速度はどれくらいなのかを分析してみます。
一般的に、試験時間の6割は解く時間に必要と言われています。
今回は、記述式である小1・小2は試験時間の4割を「読む時間」として計算し、マーク式の小3~小6は試験時間の半分を「読む時間」として計算します。
各学年の国語の問題を「読む」ために必要な読書速度は以下のようになります。
| 国語 | 読む時間 | 必要な読書速度 | 解答形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生 | 約1,600文字/30分 | 12分 | 約133.3文字/分 | 記述式 |
| 小学2年生 | 約4,000文字/30分 | 12分 | 約333.3文字/分 | 記述式 |
| 小学3年生 | 約6,800文字/35分 | 17.5分 | 約388.6文字/分 | マーク式 |
| 小学4年生 | 約8,000文字/40分 | 20分 | 約400.0文字/分 | マーク式 |
| 小学5年生 | 約9,200文字/40分 | 20分 | 約460.0文字/分 | マーク式 |
| 小学6年生 | 約10,600文字/40分 | 20分 | 約530.0文字/分 | マーク式 |
一般的に小学校低学年の平均的な読書速度は200~300文字/分、高学年は400~500文字/分と言われていますので、平均的な読書速度で読むことができれば、ひと通り問題文を読み、設問に答えていくことが可能という計算です。
ただ、問題を解くときに文章を読み返して解答する余裕はあまりありません。
マーク式の問題で選択肢の吟味をする場合には何度か問題文を読み返すこともあるでしょう。
解いた問題の見直しの時間まで確保しようとすると、平均的な読書速度の2倍くらいの速さで読めるようになっておきたいものです。
国語以外でも文章を速く正確に読み解く必要
上記の計算は国語の問題でしたが、全国統一小学生テストで時間が足りなくなってしまう悩みは国語以外の科目でもよく起きています。
例えば小学校3年生の算数の後半の大問では、最初の (1) の問題に到達する前に、問題の「設定」が詳しく書かれています。
その文字数は約350~400文字で、およそ原稿用紙1枚分です。
あわせて掲載されている図を含めて、この「設定」を理解しなければ、(1) の問題を解くことすらできないということになります。
また、理科・社会ではグラフや表について説明した文章が理解できるだけでなく、グラフや表を適切に読み取っていく必要があります。
実際に、全国統一小学生テストで初めて理科・社会の問題に取り組む小学校4年生の問題では、7~8種類の表やグラフが出題されています。
学年があがれば、単なる読み取りだけでなく、自分の知っている知識と関連させて考える必要がありますので、速く正確に読み取る力はますます重要になっていくと言えるでしょう。
理解度を落とさずに読むスピードを速めることができる速読解力講座
一般社団法人 日本速読解力協会が運営している「中学受験専門 速読解力講座」は、根本的な読むスピードを速くすることに特化した学習プログラムです。

飛ばし読みやななめ読みのようなざっくりとしか理解できない読み方ではなく、これまでの読み方の延長で、目を動かすスピードを速めたり、文字を認識するスピードを速めたり、文章の理解力そのものを高めたりすることで、文章を読む速さを2倍3倍程度まで速めることが可能です。
これまで25年以上にわたり、そのメソッドを開発し続け、これまでに全国5,500以上の学習塾や学校で導入され、累計で30万人以上が受講してまいりました。
このトレーニングをアプリを使ってご自宅で手軽に受けていただけるオンライン講座が「中学受験専門 速読解力講座」です。
無料体験も可能ですので、少しでも気になった方はお気軽にお問合せください。
(体験にあたりクレジットカードの登録や有料プランへの自動切換はございません)
⇒ 無料体験のお申込はコチラ