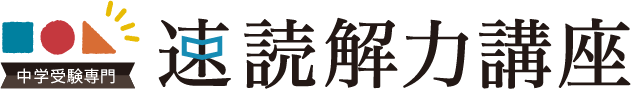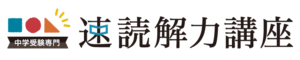開始から19年目を迎えた全国統一小学生テスト。今回も多くの小学生が挑戦したことと思います。
例年2回の全国統一小学生テストも「年間行事の一つ」として捉えている保護者の方も多いかもしれません。
今回の11月のテスト実施後は、塾の中でも徐々に「新年度」を意識するシーズンに入ってきます。
もちろん、小学校6年生が「入試」という戦いに挑んでいきますので、6月の時とは違う雰囲気を塾の先生から感じることも多いでしょう。
重要なことはテストを受けることではありません。
テストが終わった後に、受けっぱなしにするのではなく、振り返りをすることが重要です。
ここでは、テストが終わった後の「見直し・解き直し」の仕方について解説いたします。
見直しや解き直しの中でも、特に「国語」に絞って解説をしていきます。
全国統一小学生テストの小学校3年生・4年生・5年生の出題をイメージしていますので、受験した方はぜひお読みください。
全国統一小学生テストとは
全国統一小学生テストは、四谷大塚が主催する学力テストで、年に2回、無料で実施され、小学生であれば誰でも受けることができます。
2007年度に開始され、のべ400万人以上が受験している日本最大規模のテストです。
テストの出題内容は小学校の各学年の学習範囲に準拠していますが、すべての問題が小学校のレベルというわけではありません。
また、文章量・問題量ともに多いため、相当なスピードで解答を進めないと、制限時間内にすべての問題を解ききるのは容易ではありません。
全国統一小学生テストの実施教科・配点・試験時間
各学年の実施教科、配点、試験時間は以下の通りです。年長生も受験できますが、ここでは割愛いたします。
| 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生 | 30分・150点 | 30分・150点 | – | – |
| 小学2年生 | 30分・150点 | 30分・150点 | – | – |
| 小学3年生 | 35分・150点 | 35分・150点 | – | – |
| 小学4年生 | 40分・150点 | 40分・150点 | 20分・100点 | 20分・100点 |
| 小学5年生 | 50分・150点 | 40分・150点 | 25分・100点 | 25分・100点 |
| 小学6年生 | 50分・150点 | 40分・150点 | 25分・100点 | 25分・100点 |
小学3年生までは国語と算数のみ、小学4年生以降は理科と社会も実施します。
1年生は配点の70%、2・3年生は60%、4・5・6年生は55%が平均点となるように、試験問題が作成されています。
なお、1・2年生は記述式で、3~6年生はマークシート形式で解答します。
全国統一小学生テストで「時間が足りない」のはなぜ?
過去の全国統一小学生テストの問題を使って、テストを解くうえで必要な問題文・選択肢などの文字数をカウントしてみました。
以下の表では、国語の問題の文字数をもとにして、どれくらいの読書速度が必要かをまとめてみました。
一般的に試験時間の6割は解く時間に必要と言われています。
今回は、記述式である小1・小2は試験時間の4割を「読む時間」として計算し、マーク式の小3~小6は試験時間の半分を「読む時間」として計算します。
各学年の国語の問題を「読む」ために必要な読書速度は以下のようになります。
| 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生 | 約2,000文字/30分 | 約1,600文字/30分 | – | – |
| 小学2年生 | 約3,000文字/30分 | 約4,000文字/30分 | – | – |
| 小学3年生 | 約4,000文字/35分 | 約6,800文字/35分 | – | – |
| 小学4年生 | 約4,500文字/40分 | 約8,000文字/40分 | 約4,700文字/20分 | 約5,400文字/20分 |
| 小学5年生 | 約5,500文字/50分 | 約9,200文字/40分 | 約6,100文字/25分 | 約5,300文字/25分 |
| 小学6年生 | 約4,800文字/50分 | 約10,600文字/40分 | 約8,300文字/25分 | 約7,600文字/25分 |
一般的に小学校低学年の平均読書速度は200~300文字/分、高学年では400~500文字/分とされていますので、どの学年でも間に合いそうな分量と言えるかもしれません。
それなのに「時間が足りない」と感じてしまうのはなぜでしょうか。
それは、上記の「必要な読書速度」では、文章を読み返す時間はほとんど確保できないからです。
特に、マーク式の設問で選択肢を比較する際には、問題文を何度か参照することも必要になります。
解答後の見直しや確認の時間を確保するためには、平均的な読書速度の約2倍のスピードで読解できる力を身につけておくことが望ましいと言えます。
こちらについては以下の記事で詳しく解説しています。
よろしければ合わせてご確認ください。
【関連記事】 [2025年前期版]全国統一小学生テストで時間が足りない?文字数と時間配分を分析
テスト後にやるべき振り返りとは?
まず取り組みたい「振り返り」は「漢字・知識」から!
テストが終わってすぐにでも取り組んでおきたい振り返りは「漢字・知識事項」の振り返りです。
テストを解いている中でも「この漢字がわからなかった」とか「この知識が思い出せなかった」という印象が残っているお子さまは多いのではないでしょうか。
「鉄は熱いうちに打て」の教えの通り、テストが終わった直後に「悔しい」と思っているタイミングが一番良いタイミングです。
しかも、漢字や知識事項であれば比較的短時間で終えられますので、テストが終わって帰宅した後でもすぐに取り組めますね。
漢字・知識事項は、今回のテストを「きっかけ」にして覚えてしまおう!
漢字や知識事項の振り返りをしていると「この漢字は習っていない」とか「こんな四字熟語は初めて見た」のように、未習の事項が出てくるかもしれません。
子どもからすれば「習っていないのだからできなかったとしても仕方がない」と思う部分です。
もちろん、入学試験であればそのような言い訳は通用しないのですが、まだまだテストですから「じゃぁ次に同じ問題が出てきたときには正解できるように今覚えちゃおう!」と促してあげるのが良いですね。
テスト作成者は「このタイミングでこの問題ができるようになっていてほしい」というメッセージを問題の中に含めて問題を作成しています。
学校の進度や習熟度により、特に漢字や知識事項については未習の要素が含まれる可能性は出てきてしまいます。
そのような時に「習っていないから仕方ない」で終わらせてしまうのはもったいないことですので、「このテストをきっかけに」を合言葉にできたらと考えています。
読解力とは「正確に読み解く力」のこと
結果の帳票が返ってくると、まずは得点や偏差値などが気になるところだと思います。もちろん、それはチェックする必要はあるのですが、次のような2人の成績を比べてみてください。
1)国語の得点は 90/150点。漢字や知識事項はほぼ満点だが、2題ある読解問題のうち1題で得点の多くを稼いでいて、もう1題の文章題は空欄(マークなし)が目立っている。
2)国語の得点は 90/150点。漢字や知識事項も、2題ある文章読解もいずれも6割程度の正解率。解答用紙はすべて埋まっている(マークはすべて塗ってある)状態。
さて、1と2のどちらも、総合得点は90点で満点の6割ですが、答案の状況は大きく異なりますね。
どちらの方が「読解力のある子」と言えるでしょうか。
正解率から考えれば、1のほうが読解力があると言えるでしょう。一方で、最後まで解けたという点では2のほうが読解力があると言えるかもしれません。
入試では「書かれている内容を正確に読み取り、問題に答える」ことが求められている以上、ここでは正解率の高いほうが得点が安定するという意味で、読解力があると考えていきます。
試験の「時間配分」も振り返りましょう
試験全体を解く順番は漢字・知識からがよい…というのは国語の試験を解くうえでは半ば常識のようになっていますし、塾でもそういった指導がされることがあると思います。
(まだそんな話を聞いていない、というお子さまでも入試が近づくことで耳にする機会があるはずです)
さて、漢字・知識問題の分量にもよりますが、試験全体の中で読解問題にどれくらいの時間を掛けられていたでしょうか。
試験中に時間を記録していることは稀だと思いますので、お子さまがどのような感想をお持ちか、確認してみてください。
例えば「文章題1つめで時間を取ってしまい、2つめはじっくり考えられなかった」とか「文章題1つで時間ぎりぎりだった」とか「最後の2問ぐらいは時間がなくて適当に答えた」とか、いろいろな反応が返ってくるのではないでしょうか。
じっくり読めばわかるのかどうか…が読解力の第一歩
もし「時間が足りなくて、文章題の2つめは思うように解けなかった…」というのであれば、ぜひ「時間は無制限でいいから、この2つめの文章題を納得がいくまで解いてみよう」とトライさせてみてください。
もちろん、集中力もそこまで持たないので国語全体の試験時間を目安にする必要はありますが、それでも40分で2題の文章題が含まれているテストのうちの1つの文章題を40分掛けて解いてよいとなれば、じっくり考えて解くことができるようになります。
これで解いた時に、例えば平均点ぐらいの点数が取れるようであれば、その学年の文章問題の読解力については概ね問題がないということになります。
どのようなタイプの問題でミスが多いのかも確認
さて、ここからが「国語としての見直し」の部分になりますが、間違えてしまった問題にはどのようなタイプの問題が多いのか、確認していくことが必要です。
設問文や解答・解説から設問のポイントは把握できますが、不安な場合はこれまでに学習していたテキストの似た形式の問題と照合してみると良いでしょう。
物語・小説文であれば、場面を捉える問題・心情把握の問題・主題を正しく理解する問題などがあります。
特に、心情把握の問題は入試では頻出の問題ですので、不安がある場合には解き方を復習しておくようにしてください。
登場人物の関係性や時系列が把握できていないと、文章全体を理解できていない可能性もありますので、丁寧に読み込むようにしましょう。
説明文・論説文であれば、話題と結論が把握できているか、指示語・接続語は正しく理解できているかどうか、筆者の主張を捉えられているかなどがポイントになります。
「簡単にまとめるとどんな話だった?」のような問いかけで、話題と結論を理解できているかをチェックすると良いでしょう。
読み取りやすい「具体例」ばかりに目が向いてしまう場合は、抽象・具体(上位語・下位語)の関係も理解する必要があります。
知っている語彙の数を増やそう
説明文・物語文では、抽象・具体の関係だけでなく、話題に関連した語彙をどれだけ知っているかで文章の読解のしやすさは変わってきます。
また、物語・小説文では「心情語」に関する知識が多ければ多いほど、心情の細やかな変化に気づくことができます。
語彙を増やすというと、どうしても漢字や知識の勉強に結びついてしまいがちですが、通常の読解問題を読みながらでも、気になる単語を調べるようにしたり、覚えた単語を使ってみたりすることで、語彙の量は増やすことができます。
この「実際に使ってみる」というのも大きなポイントで、実際に発信してみようとすると、周辺の文脈なども考えなくてはいけなくなり、語彙に関する理解が深まり、単なる知識だけではないレベルに引き上げることができます。
次のステップとして「速さ」のトレーニングも
ある程度文章読解ができるようになったら、徐々に速さのトレーニングもしていきたいところです。
ここまでは国語の見直しに特化して解説をしてきましたが、全国統一小学生テストの他の科目でも文章量は多いという印象を持たれたお子さまも多いかと思います。
実際の入試問題も、もちろん学校にはよりますが、国語以外の科目での文章量は増えています。
特に、公立の中高一貫校の適性検査や、それに近い出題がされる適性検査型の入試問題はかなりの分量を読んで条件を整理して解く問題が多く出題されます。
小学校6年生の夏期講習会以降で過去問演習が本格化する中で、自分の志望校の入試問題のタイプ(問題文の長さや記述量の多さなど)がわかってきます。
ただ、それを待つのではなく、受験学年を迎える前に「速く正確に文章を読み解く力」を身につけておくことは、受験勉強を有利に進める上で必須の要素と言えるでしょう。
理解度を落とさずに読むスピードを速めることができる速読解力講座
一般社団法人 日本速読解力協会が運営している「中学受験専門 速読解力講座」は、根本的な読むスピードを速くすることに特化した学習プログラムです。
飛ばし読みやななめ読みのようなざっくりとしか理解できない読み方ではなく、これまでの読み方の延長で、目を動かすスピードを速めたり、文字を認識するスピードを速めたり、文章の理解力そのものを高めたりすることで、文章を読む速さを2倍3倍程度まで速めることが可能です。
これまで25年以上にわたり、そのメソッドを開発し続け、これまでに全国5,500以上の学習塾や学校で導入され、累計で30万人以上が受講してまいりました。
このトレーニングをアプリを使ってご自宅で手軽に受けていただけるオンライン講座が「中学受験専門 速読解力講座」です。
無料体験も可能ですので、少しでも気になった方はお気軽にお問合せください。
(体験にあたりクレジットカードの登録や有料プランへの自動切換はございません)
⇒ 無料体験のお申込はコチラ