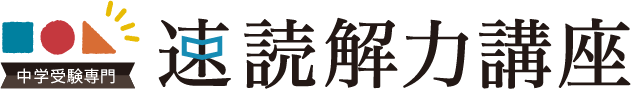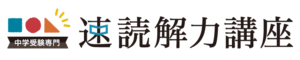はじめに
少しずつ肌寒くなってくると、塾からの新年度募集のお知らせを目にする時期になります。
「まわりのお友達も中学受験をすると言っているし…」「そろそろ塾を…」と検討を始める時期になるのではないでしょうか。
ここでは、中学受験に向けて、塾の新年度開講までの間に取り組んでおきたいことをお伝えいたします。
2.中学受験は2月からが新年度!
2-1.入試まであと100日を切って…
中学入試本番へのカウントダウンはすでに始まっています。
首都圏の中学入試のうち、東京・神奈川の解禁日は2/1で、10/24が100日前にあたり、本番を控えた受験生はいよいよカウントダウンの中で、追い込みと最終調整に励んでいることと思います。
一方で、埼玉県・千葉県の中学入試は1月からスタートします。
想像されている以上に早めのスケジュールで中学受験は進んでいくという印象をお持ちになるかもしれません。
2-2.塾の新学年スタートは「最初から全力」です
塾の新学年は2月からスタートします。
この「スタートする」のイメージはどういったイメージを持つでしょうか。
小学校の「スタート」だったら、最初のうちは先生に慣れたり、比較的易しいことを学んだりしながらゆっくりスタートをしていきます。
仮にこの部分での積み残しがあっても、そのまま復習しながら進めていくことができます。
それに対して、塾の「スタート」では、初回から中学受験カリキュラムが詰め込まれています。
多くの方が中学受験を開始する新小3や新小4でも、学校の勉強とはレベルの違う内容が次々と展開されていきます。
その内容を受けとれる準備をしておくことが必要になります。
仮に、スタート段階で積み残しがあると、それは「後で『なんとかなる』」ではなく、「後で『なんとかする』」という意識が必要となります。
2-3.学習への意識を変えること
少し具体的に話をしますが、例えば漢字テストを例にとってみましょう。
「来週までにこの漢字10文字を覚えてきなさい。来週はそれぞれの漢字について熟語が2問ずつ出題される合計20問、100点満点のテストを実施します」と指示が出されたとします。
ここで学ぶ漢字は中学受験カリキュラムに基づいているものだとすると、小学校で学んでいない漢字が含まれています。
ここで「学校で習っていないから…」とか「漢字の覚え方がわからないから…」と考えているとどんどん差が広がってしまいます。
「自分の場合は漢字をこうやって覚える」「学校で習っていなくても練習していい点を取ろう」と考えられるようになってほしいと思います。
もちろん、最初から満点を取らないとダメだというわけではありませんが、「できなくても仕方ない」というのは頑張った上での話であって、最初からそれを頑張らない言い訳にしないことが重要です。
3.全国統一小学生テストが終わり…
3-1.全国統一小学生テストとは
全国統一小学生テストは、四谷大塚が主催する学力テストで、年に2回、無料で実施され、小学生であれば誰でも受けることができます。
これまでに、のべ400万人以上が受験している日本最大規模のテストです。
これをお読みの方の中にも、このテストをきっかけに中学受験を考えたという方も多いのではないかなと思います。
3-2.初めて受験したら「時間が足りない」のでは…?
小2生で算数・国語が各30分、小3生では各35分、小4生では各40分の算国に加えて理社が各20分です(その他の学年は割愛します)。
初めて受験された方は「時間が足りない」という感覚だったのではないでしょうか。
それはある意味では正しい反応で、国語の問題を例にとって求められている「読む速度」を計算してみると試験時間の余裕はあまりないと言えます。
国語の選択肢の吟味で時間がかかったり、算数の難しめの問題で考え込んだりしていると、見直しの時間も確保できずに終わってしまったのではないでしょうか。
▶関連記事:全国小学生統一テストで時間が足りない?文字数と時間配分を分析
また、算数の最後の方の問題は、例年正答率が1%程度とかなり難しい問題になっています。
条件が複雑だったり、問題文そのものが長かったり…。
これまで学校の勉強しか触れてこなかったお子さまにとっては「見たことのない問題」だったかもしれませんね。
3-3.点数よりも大事なこと
テストが終わると、どうしても点数や偏差値に目が向いてしまい、その点数や偏差値をもとにして「これができていない」とか「ここを何で間違えたのか」とどうしても「悪いところ」に目が向きがちです。
ただ、まだ塾に通っていないお子さまが、慣れない環境で全国統一小学生テストを受験したことは、それだけでも称賛に値することではないでしょうか。
まずは、最後まであきらめずにテストに果敢にアタックしたお子さまのことを褒めてあげるところからスタートしたいところです。
そして、この考え方は、これから先の中学受験を「本人・保護者・塾」の三者が一体となって進めていくうえでも重要な要素の一つです。
この先、塾の授業だけでなく、外部会場で受験する模擬試験や学校見学・説明会など、初めての環境に触れることが増えてきます。
その時に「よくがんばったね」というポジティブな言葉から始められるといいですね。
3-4.各塾の先生に相談を
お子さまの実力は点数・偏差値だけでは測れません。
各塾では、この時期、点数・偏差値からは見えてこない部分をしっかりと分析して、学習のアドバイスをしてくれます。
例えば、算数で同じ90点(150点満点)だとしても、最初の計算問題が全部できている90点と、易しい問題でのミスが目立つ90点とでは、学習アドバイスは異なります。
お子さま一人ひとりのアドバイスをしてもらえますので、お近くの塾にまずはお問い合わせしてみるとよいでしょう。
4.新年度からの入塾前にやっておきたいこと
4-1.わからないことにワクワクできる
中学受験を始めるにあたって、まず大事なことです。
中学受験カリキュラムで学習する内容は、小学校での学習と比べると「知らないこと」が多く出てきます。
国語の漢字・語句に関する知識、算数の計算方法(いわゆる特殊算も含まれます)、理科・社会の知識など…。
その「知らないこと」を『ワクワクした気持ち』で学べるかどうかは、長い中学受験カリキュラムを乗り越えていく上でも必要な要素の一つです。
「塾に行ったら新しいことが学べて楽しい」と思えるようになるとよいですね。
4-2.書かれていることを正確に理解する
これは科目に関わらず重要な要素であることは言うまでもありません。
書かれていることを正しく理解することができなければ、国語の文章はもちろん、他の科目でもおかしなミスをしてしまうことに直結します。
文の中で書かれている重要なことは何か、算数であれば必要な数字の情報はどれか…といった要素を速く正確に理解できれば、思考力を必要とする問題で「考える時間」を確保できることにもつながります。
例えば「動物園にキリンが3頭、ペンギンが10羽います。動物園にはゾウもいますが、ゾウはキリンより2頭多くいます。ゾウは何頭いるでしょうか」のように、この段階では関係ない情報(ペンギンが10羽)を削って(=必要な情報だけを抽出して)理解することができれば、計算処理の段階で迷うことはありませんね。
なお、実際に発達心理学の研究でも、文章題の難しさの原因の多くは問題理解過程にあること、問題文から抽出した必要な数字の関連づけがつまずきの原因になっていることがわかっています。
4-3.時間の使い方のイメージを作っておく
通塾が始まると、平日であれば、小学校の授業後の夕方~夜の時間帯で塾の授業が入り、そこに宿題などが追加される形になります。
これまでは友だちと遊ぶなどの自由時間だったところが塾の学習に費やされるイメージですから、これまでよりも自由時間が減ると捉えてしまうお子さまも少なからずいらっしゃると思います。
塾が本格的に始まる前に、1週間の時間の使い方のイメージを作っておけると良いでしょう。
そのためには、塾ではどれくらいの授業時間があって、どれくらいの宿題が標準的に課されるのかを知っておくと、イメージを作りやすくなるでしょう。
宿題についてはもちろん個人差がありますし、カリキュラム内容によっても掛かる時間は前後します(例えば国語なら説明文と物語文で宿題の時間は変わります)。
新年度が始まる前の冬期講習会や1月の授業などを活用して、実際に「塾がある生活」を体験してみることで、新年度からの準備を万全にすることができるでしょう。
[参考文献]
・坂本美紀 (1993)「算数文章題の解決過程における誤りの研究」、『発達心理学研究』第4巻、第2号、p.117-125.
理解度を落とさずに読むスピードを速めることができる速読解力講座
一般社団法人 日本速読解力協会が運営している「中学受験専門 速読解力講座」は、根本的な読むスピードを速くすることに特化した学習プログラムです。
飛ばし読みやななめ読みのようなざっくりとしか理解できない読み方ではなく、これまでの読み方の延長で、目を動かすスピードを速めたり、文字を認識するスピードを速めたり、文章の理解力そのものを高めたりすることで、文章を読む速さを2倍3倍程度まで速めることが可能です。
これまで25年以上にわたり、そのメソッドを開発し続け、これまでに全国5,500以上の学習塾や学校で導入され、累計で30万人以上が受講してまいりました。
このトレーニングをアプリを使ってご自宅で手軽に受けていただけるオンライン講座が「中学受験専門 速読解力講座」です。
無料体験も可能ですので、少しでも気になった方はお気軽にお問合せください。
(体験にあたりクレジットカードの登録や有料プランへの自動切換はございません)
⇒ 2週間の無料体験をしてみる
無料体験のお申込みはこちら